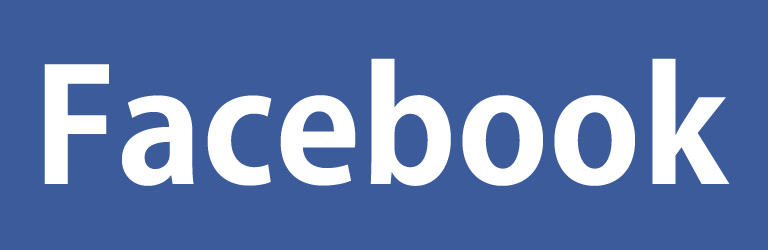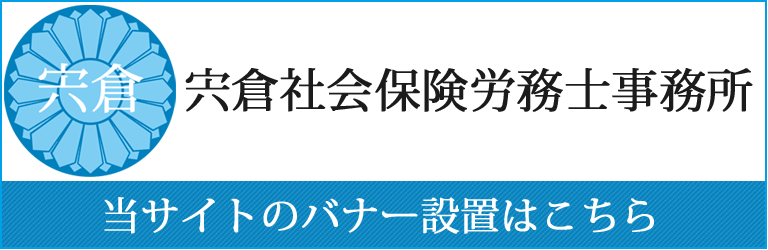宍倉社労士の労務相談室ー起訴休職制度について
平成30年12月
今回は、起訴休職制度について取り上げます。今年の暮れの大きな話題といえば、先月の日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン氏の逮捕。逮捕された後に間髪を入れずに会長を解任されたことも、特に海外メディアで大きく取り上げられたのは皆さんご存知の通り。
カルロス・ゴーン氏は会長職、つまりは、従業員ではなかったのでそのような処分となってしまいましたが、実際に会社の一般の従業員が逮捕された場合どうなるのかということを考えたいと思います。
一般従業員の懲戒処分は刑が確定するまでは難しい
従業員の場合は、会社との雇用契約により就労しておりますので、使用者側が一方的に雇用関係を終了させる場合は『解雇』にあたり、労働契約法の16条にある解雇法理が適用されます。
無論、問題行為があった場合は懲戒処分が出来ますし、内容によっては懲戒解雇も可能ですが、ただ単に逮捕されたというだけでは懲戒処分はできません。
つまり、司法の場などで有罪か無罪かなどがはっきりとするまでは、『推定無罪』の原則に則り処分はできないということになります。より正確に言うと、結果がでる前に会社で懲戒処分を行うと、最終的に無罪となった場合には、後になってその懲戒処分が無効とされる可能性が高いということになります。
この件については弊所のメルマガでも配信したテーマですので、ご興味ある方はメルマガ登録お願いします。
刑が確定するまで長期戦になる場合
従業員が逮捕されるケース様々ありますが、痴漢行為(強制わいせつ)や職場内外での喧嘩(傷害罪や暴行罪)によるものが多く見られると追いえます。こうした犯罪で逮捕された場合に、不起訴処分が決定する等して比較的短期間で決着がつき、周りの従業員も気付かないまま職場に復帰できる場合もありますが、逆に一旦起訴されてしまい長丁場となることも珍しくありません。
この長丁場の状況になったときに、当該従業員をその間どのような扱いとするのかが問題となります。
起訴休職とは
起訴休職とは、休職制度の一環で、従業員が刑事事件等に巻き込まれ、起訴された場合に休職扱いとする制度です。就業規則上で明確に『起訴休職』という制度としている場合もあれば、起訴されたときに「会社が必要とする特別な事由」として休職させる場合がありますが、どちらも本質的には同じといってよいでしょう。
前述の通り、起訴されてしまうと長期間「結果を待つ」状況が続きます。この間「疑われている状況」で就労させることは本人にとっても、周囲で働く従業員にとっても働きにくい状況となることが容易に想像されます。この期間に休職させることで職場の環境を維持する制度が起訴休職の目的です。
一般的な話ですが、強制わいせつの場合には、職場の異性から、「このような人と一緒に仕事をしたくない」という苦情が寄せられることも多い。その一方で、従業員同士の喧嘩が原因だった場合に当事者同士が同じ職場にいる場合もあり、そのまま就労させること自体に問題があるとも考えられますので、こうした場合に有効な制度ということも出来ます。
起訴休職制度の留意点
起訴休職制度はこのように一定程度のメリットがある反面、運用には注意しなければならない点が多くあります。
起訴後の身柄確保の状況
起訴休職の制度がある場合、実際に休職させるかどうかの判断に当たり、大変重要なのが、起訴後に当該従業員の身柄がどうなっているかということです。長期に亘る拘留などで、そもそも会社に出勤できない状況にあるのか、それとも身柄は確保されておらず、就労しようと思えばできる状況にあるのか、という違いは非常に大きな違いです。
起訴休職期間中の賃金支払いについて
また、制度の設計上考慮しなければならない重要事項は、起訴休職期間中の賃金です。調査によると、起訴休職を導入している企業のうち、当該起訴休職期間中の賃金を無給、或いは、大幅な減額支給としているところが非常に多いという結果がでています。ある意味「自分でまいた種」という厳しい言い方もできますが、本人が無罪の場合は非常に厳しい対応ともいえます。
起訴休職期間中を無給とすると、傷病手当金の支給が期待できる私傷病による休職と違い、起訴休職期間中全くの無収入となるので、本人にとっての影響は非常に大きなものとなります。
このため、起訴休職とさせたこと自体が有効か無効なのかを争う裁判に発展するケースも少なくありませんので、賃金の支給については慎重に制度を作る必要があります。
判例が示す留意点
前述の通り起訴休職の期間中賃金を無給(或いは大幅減)とした場合、争いに発展することは珍しくありません。司法において、起訴休職を有効とするか無効とするかについては以下2つのポイントで判断するとされています。
① 引き続き就労させることが会社の対外的信用を失墜させる場合、または、就労させることで職場の秩序が維持できなくなる場合。
② 頻繁に裁判所に呼ばれるなど、労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が発生する場合
前述の通り、そもそも身柄が確保されていて、就労しようと思っても就労できない状況にある場合はこの②にあたります。実際に雇用契約に沿った労務提供ができない訳ですから、起訴休職が認められる可能性は高いといえます。これに対し、身柄が確保されておらず、「働こうと思えば働ける」状況にあるのに、会社が起訴休職を適用することで、実質的に就労を拒む場合問題がでると考えられます。
運用上の留意点
そこで、身柄が拘束されておらず、労務の提供ができる状況で起訴休職を適用する場合の注意点をここで整理します。
前提としなければならない考え方
起訴休職の適用を考えるにあたって重要なことは、起訴休職は懲戒処分ではないということです。
冒頭で説明のとおり、懲戒処分は最終的な結論がでるまで行うことにはリスクが伴いますが、起訴休職は懲戒ではなく、起訴されたこと自体をもって休職させる制度です。「悪いことをしたから」休職させるのではなく、「この状況で働いてもらうと困るから」休職してもらうという考え方を徹底しなければなりません。従って、結果的に有罪になるか無罪になるかに関係なく、休職させる必要があるかないかという観点で休職させるかどうかの判断を行わなければなりません。
つまり、採取的に無罪であったとしても、就労させるべきではない状況もあれば、有罪だったとしても就労を拒む理由にはならない(就労させるべき)状況もあるということです。
会社の対外的な信用を失墜させるか
まだ疑いがある段階であったとしても「そうした犯罪行為を行った従業員がいる会社とは取引できない」というような、社外からの信用や評判で会社の対外的な信用に影響するかしないかという観点で考えることになりますすることになります。
例えば、マスコミで大きく報道されるなどして、社会的に注目される環境にあるのか、或いは、その事実が全く知られていないのかによっても大きく変わります。
さらに、当該従業員がどのような業務についているのかも重要な要素となります。企業の顔とも言うべき広報担当であったり、点等での窓口業務や運送事業での運転し・パイロットなど普段から接客をする業務であったり、または、他人を指導するような、いわば露出度の高い仕事を行っている場合は、より問題となるでしょう。これに対し、「表」にでることはない、事務のデータ入力をしている業務であれば影響は小さいといえます。
<チェックポイント>
*事件自体が対外的にどの程度認知されているか
*当事者従業員自身がどの程度社外で知られる存在なのか
*当事者従業員が外部と接する業務を行うのか
職場の秩序が維持できるか
就業させるべきかどうかのもう一つの観点は、職場に与える影響です。起訴された当事者が職場で就労することで、周りの就労環境に悪影響があるかどうか、企業の指揮命令系統が正常に機能するのかといった観点でしょう。
これについては、傷害事件の加害者と被害者が同じ職場にいる場合は、一定の配慮が必要なのは言うまでもありません。配慮の一環として休職させることも正当な判断といえる場合もあります。また、その非違行為の内容によっては、職場での信頼関係が崩れるということも考えられます。例えば、詐欺行為など、人としての信頼にきわめて重要な事件で起訴された場合、職場の秩序維持から休職させることもやむを得ないといえます。こうしたことを基準に判断することとなります。
<チェックポイント>
*どのような非違行為だったのか。その非違行為によって当事者従業員に対する信頼が著しく損なわれているのか
*当事者従業員が事件事案の被害者を始め、ほかの当事者と業務上接点を持ち得る環境にあるのか
最後に
起訴休職制度は、起訴されただけで休職させることができる制度です。この制度での休職は賃金が大幅に減額されるか無給とされることが一般的で、当事者にとっては被告人となった上に賃金もないという極めて厳しい立場に立たされることになります。
それ故、制度の導入、及び、個々の事案で休職させるかどうかについては慎重な判断が求められるといえます。
実際の制度導入のご相談はご相談下さい
宍倉社会保険労務士事務所 (東京会渋谷支部所属)
電話 03-6427-1120
携帯電話 090-8595-5373
メール shishikura@ks-advisory.co.jp
住所 東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル204