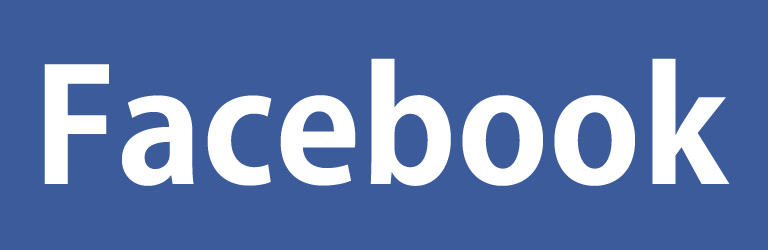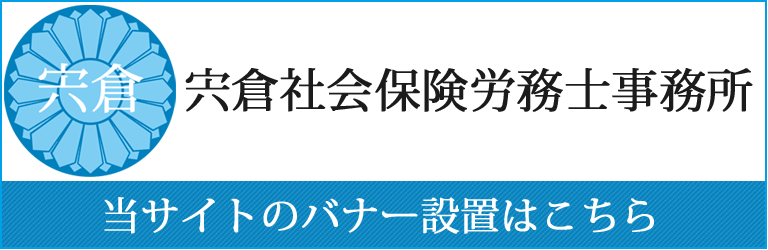労働裁判から学ぶ メトロコマース事件 同一労働同一賃金における退職金の支給を解説
令和2年10月
10月中旬は同一労働同一賃金にとって極めて重要な司法判断が示される。
13日には契約社員に対する賞与の支給の有無が不合理な待遇差にあたるか争った大阪医科大学事件、契約社員に対する退職金支給の有無が不合理な待遇差となるか争ったメトロコマース事件。
15日には日本郵便の従業員が訴訟を起こした3件(東京・大阪・福岡)の事件についてまとまった判断が示される。
本投稿では、メトロコマース事件の判断を解説する。
高裁までの判断
上告審までの経緯
本件は、東京メトロの関連会社で主に地下鉄駅構内で販売業務を行ういわゆるキヨスクの業務を展開するメトロコマース社に対し、元従業員が正社員との待遇が不合理として訴えを起こしていたもの。
主な争点は退職金・住宅手当・褒賞・時間外労働に係る割増率、それぞれにおいて訴えを起こした契約社員と正社員との間の待遇差が不合理なものかという点であった。
退職金以外の手当については待遇差が不合理との結論を出した高裁の判断がそのまま認められたが、退職金については9月に上告審弁論が開かれ、今回最高裁で判断を下すこととなった。
地裁および高裁の判断
一審の東京地裁は平成29年3月に不合理な待遇差はないとの判断を示していた。この根拠としては、契約社員は販売員業務から変更になることはないのに対して、正社員には業務が変更になる可能性があり、いわゆる「変更の範囲」に相違がある等としていた。
これを受けた東京高裁は、地裁が判断したように職務の内容や変更の範囲に一定の違いがあることを認めた上で、退職金支給の趣旨に触れ、永年の功労に対する報償の性質があり、契約社員といえどもゼロ支給は問題との考えを示した。
具体的には、10年以上勤続した社員に対しては正社員の25%程度の退職金は支給すべきとの考えであった。ある種画期的な判断とされていた。
高裁判断については以前投稿した内容をこちらから確認ください
最高裁の判断
この高裁判断を受けて最高裁の判断が注目されたが、結論としては待遇差は不合理ではないとの判断を下した。東京高裁が示した「正社員の25%」という点についても否定した形になる。判断根拠については以下整理するが、今回の判断でもう一つ注目に値するのはこの判断に反対意見が示されたことといえる。
今回の判断は5名の裁判官によるものであったが、1名が反対し、賛成した4人のうち2名は補足意見を付したことに注目したい。
最高裁の判断
メトロコマース社には、正社員・契約社員A(後に「職種限定社員」に改められた)・契約社員Bの3種類の社員が存在。今回の訴訟は契約社員Bであった4名の社員が起こしたものであった。その契約社員Bと正社員との職務の違いなどを比較すると以下の差があったと判断された。
<職務内容の相違>
正社員は契約社員が欠勤した場合に欠勤する契約社員に代わってシフトに入る(代務業務)の責任があることや一定の地区内の複数店舗を統括するエリアマネジャー業務に従事することになっていたのに対し、契約社員Bはその任務を担うことがなかった。このことから職務内容に一定の相違があったと判断。
<変更の範囲>
正社員は販売店の業務を行っていても他の業務への配転等を命じられる可能性があり、正当な理由がなくこれを拒否できない。一方の契約社員Bについては業務の場所の変更はあっても業務内容の変更を命じられることはなかった。このことからいわゆる「変更の範囲」にも一定の相違があったとされた。
<その他の事情>
最高裁は「その他の事情」として、メトロコマースにおいては登用試験制度があり、試験に合格すれば契約社員B⇒契約社員A、そして契約社員A⇒正社員となることができ、この制度の適用を受けた社員も相応数みられたことで地位が固定的ではないことも考慮したとした。
上記の通り、職務の内容と変更の範囲に一定の相違があることをもって、契約社員Bに対して退職金を支給しないとする待遇差は不合理とまでは言えないとの結論を導いた。
反対意見について
上記の結論に対して反対意見を述べた裁判官は以下の判断を示した。
<職務内容及び変更の範囲の相違について>
職務内容については契約社員Bであっても代務業務を行うこともあり、代務業務が正社員にしかできないという専門的なものではないこと。さらに、エリアマネジャー業務が一般の販売業務の内容とどれほど質が異なるかは疑問とした。
また、変更の範囲については正社員は「制度上」は異動があるが、販売店に勤務する正社員は本社の各部署や事業所に配置される正社員とは明らかに異動の範囲が異なり、そうした本部スタッフがローテーションで一時的に販売店で勤務しているとは異なるとの考え方を示した。
こうしたことからいずれも一定の相違があるものの、それほど大きな差がないとの判断を示した。
<継続的な(長期)雇用を前提としていた>
契約社員Bは契約期間を1年としているが、労働契約は原則として更新され、定年を65歳と定めていることから65歳までの勤務が保証されている。正社員の多くが出向者として(親会社等から)受け入れているため雇入れの年齢が高いことを踏まえると、契約社員Bの方が長期間勤務する場合が多く、継続的な勤務に対する功労報償という性質を含む退職金は契約社員Bにも当てはまるとの考えを示した。
<結論>
退職金に係る条件に相違があることは不合理とは言わないが、正社員の25%は支給すべきと判断した高裁の判決を破棄するには及ばない。とした。
補足意見について
補足意見については2名の裁判官が同じ意見として以下捕捉した。
「企業等において退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的をも十分に踏まえて検討する必要がある」とした上で、有期雇用労働者であっても長期雇用を想定して採用されている場合で職務の内容が実質的に異ならない場合には退職金の相違が不合理となる場合があるとした。
つまり、ケースバイケースで判断されるべきとした。
最高裁の判断を事業主はどのように人事制度に活かすべきか
賛成の裁判官2名が補足したとおり、ケースバイケースで考える必要があり、契約社員に対して退職金の支給は不要と結論付けるべきではない。
今回の判断の疑問点
高裁判断が全く否定されたことには筆者として残念に思う。
確かに退職金の支給趣旨が何であるか、長年の功労報償の要素がどの程度含まれているとするのか、この測定は事実上不可能と考える。このため、高裁が示した25%支給という根拠も乏しいとは考える。
その一方で、「職務や変更の範囲に一定の差があったとしても、待遇差は『その差に応じた』ものであるべき」との考えが同一労働同一賃金ガイドラインで示されていただけに、いわゆるゼロ回答となったことは疑問に思う。
同日最高裁で判断が下された大阪医科大学事件における賞与を支給しないことを不合理としない判断もそうであるが、結論は100-0ではないのではないかとの印象を持つ。
やはり、職務や変更の範囲の違いに応じた考え方が必要ではないかと考える。この点については将来の司法判断を待ちたい。
人事制度・退職金制度に活かす
本最高裁判断を参考に、人事制度、退職金制度の構築にあたって参考にすべき点を2つ挙げる
① 支給趣旨を明確に数ること
補足意見に示されたように退職金のように複合的な性質を持つ待遇については、それを支給する目的を十分に踏まえることが重要になる。退職金をどのように支給するかの裁量は使用者にあるとの見解が今回の裁判では示されていることを勘案すると、使用者としては「何となく」退職金制度を設けるのではなく、退職金を支給する目的を明確にすることも重要と考える。
② 正社員登用制度を設けること
本裁判でも示されたが、同一労働同一賃金の裁判ではこれまでも同様の考えが示されているが、地位の固定がなく、契約社員から正社員になることを可能とすることが待遇差が不合理かどうかの判断に影響することが明らかでる。
契約社員と正社員との待遇差が不合理と判断されないためにもこうした登用制度を設け、契約社員が正社員になることができる道を張らくことは重要と考える。
宍倉社会保険労務士事務所
住所 東京都渋谷区渋谷1-4-6-204
電話 03-6427-1120
携帯電話 090-8595-5373
メール shishikura@ks-advisory.co.jp