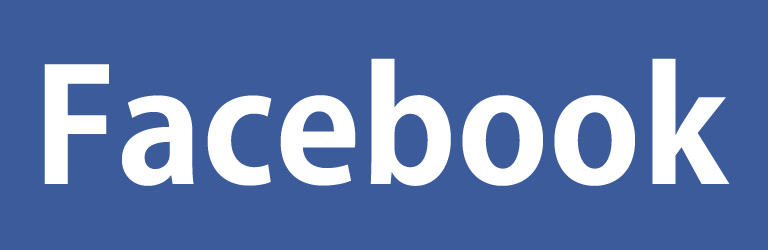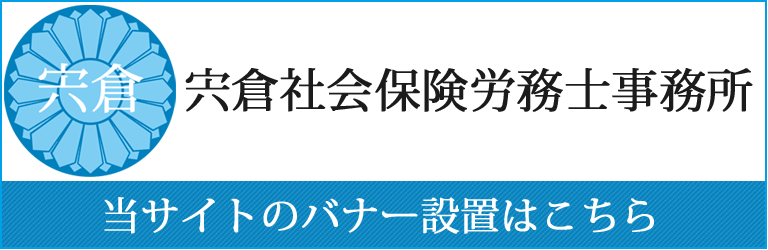労働裁判から学ぶー無期転換への対応は正しくできているか
令和4年1月
今回取り上げるのは先日東京地裁で下された無期転換を巡る判断。本件では地裁が無期転換権が発生しているとした原告の主張を全面的に認め、原告側の職場復帰が認められたというもの。また、地裁の前段階で労働審判も行われており、労働審判の場でも同様の判断が出されていた。
使用者は納得していないようだが、個人的な意見としては、司法の判断は極めて妥当と考える。
そこで、無期転換のルールを改めて確認し、無期転換に正しく備えるために必要な準備を再確認する。
事件の概要と判決
本件は外国の航空会社の客室乗務員(以下、「CA」という)として雇用された3名の契約社員が雇い止めされたことを違法として、無期雇用に転換したことの確認を訴えたもの。
事件の概要
原告側の3名のCAは2014年3月に航空会社に雇入れられ、最初約2か月の期間は『訓練契約』という形式で航空会社の本社がある国の施設でCAとしての訓練を受けた。その後『契約社員』という雇用形態で正式にCAとして勤務。この契約社員としての勤続年数が5年であったという。3名の契約社員は2019年5月に雇い止めされたとされている。
ポイントとなるのは、訓練契約の期間をどう解釈するかである。この約2か月の期間を勤続期間に含めた場合、合計の勤続年数は5年を超えることになるため、無期転換権が発生していることになり、使用者側はこの無期転換の請求を拒むことができない。
原告側は、訓練契約も勤続年数に含まれるため無期転換権が生じていると主張して、無期転換を認めない使用者の対応が違法として訴えたもの(最初は労働審判)である。
地裁の判断
東京地裁は「訓練は同社のCAとして乗務するのに必要不可欠で、従事すること自体が業務の一環」と指摘。さらに「訓練期間中も労務提供していたと認めるのが相当だ」とした。従って、この訓練契約とされていた期間も労務提供があるため、勤続期間に含まれるという判断を下した。結果として原告側の主張を全面的に認めたといえる。
労働とは?教育訓練と労働時間
ここで「労働とは何か?」ということを改めて考えたい。まず、労働者とは「使用者の指揮命令下に置かれ賃金を支払われる者」とされているが、今回問題とされた教育研修を受けている時間は労働なのかどうかを整理する必要がある。基本的には、使用者により必要な教育訓練を受けることを指示され、その対価として賃金を得ている場合は立派な労働ということが言える。
本件における『訓練契約』の契約内容(労働条件)の詳細は承知していないが、少なくても航空会社の指示で本社の訓練施設に行き、CAに必要な訓練を受けているのであるから、労働以外の何物でもない。
もう少し身近な例で再確認しよう。大手企業が新卒社員に対して行なう新入社員研修に参加する行為、
あるいは、企業が従業員に受講することを義務付けている研修会に参加する行為は、それが業務時間中であるかどうかにかかわらず、また、社内研修か社外の研修であるかにかかわらず、労働になると考えられ、賃金が当然に発生する。また、当然勤続期間に含まれるべきである。
これに対し、従業員が「自己啓発」の一環で自主的にセミナーに参加する場合は労働時間に含まれず、賃金も発生しないと考えられる。ただし、『自主的に』という名目の下、研修会への参加・不参加が人事に直接影響する場合など、事実上の指揮命令がある場合は、それが労働とみなされる可能性が高い。
本件では、裁判所の判断の通り、CAの業務を遂行するのに必要な研修を使用者の指示で受けていたのであるから、それが『訓練契約』という名目であったとしても通常の雇用契約と変わりがなく、無期転換を語る上での通算契約期間に含まれると考えるのは自然であるといえる。
結論から言えば、CA候補者が自費で自主的に研修会に参加し、そしてその教育訓練に参加したかどうかが契約社員として採用に直接影響しないという状況でない限り、今回の使用者の主張には無理があると考える。
無期転換ルールとは
ここで少しだけ無期転換ルールの基本に触れる。無期転換ルールは2013年に改正された労働契約法18条に定められており、事実上は改正法施行から5年経過後の2018年以降影響が出ている。
事実上の運用開始から3年以上経過しているので皆さんもルールについては承知しているものと思うが、ここでポイントとなるのは『通算契約期間』の考え方である。通算契約期間は勤続年数とは異なることは改めて抑えていただきたい。詳細の説明はここでは割愛するが、詳しく知りたい方は、小職が2017年に行なった投稿をご覧いただきたい。投稿はこちらをクリックください。
最初の訓練契約の終了後、改めて契約社員としての有期雇用契約を1年契約で締結し、その後毎年更新していたと仮定した場合に、契約社員として満4年勤務した時点で通算した勤続年数は4年2か月となる。この時点で新たに1年契約を締結したとすれば、契約締結時点で通算契約期間が5年を超えることとになる。
つまり、契約社員としての5年目の契約を締結した(2018年6月時点)頃、既に無期転換権が発生していたと推察できる。
使用者が押さえておくべきポイント
2013年の労働契約法改正により無期転換ルールや雇い止め法理が整理された。さらに同一労働同一賃金のルールも整備されたことで、使用者は有期雇用の労働者についての考え方を整理しなければならない。これまでは有期雇用契約での雇用はある意味使用者にとって都合の良い形式であったが、今後は十分に注意が必要となる。そこで、有期契約で雇用する労働者について無期転換の観点で整理すべきポイントを以下整理する。
有期雇用労働者の位置づけをはっきりさせること
有期契約によって雇用している労働者の通算契約期間が5年を超えれば無期転換権が生じ、そこで無期雇用への転換を求められた場合に使用者は断ることができない。これが無期転換ルールの基本である。
そこで、使用者にとって最も大切なのが、有期雇用の労働者を雇い入れる時点で長期雇用する考えがあるかどうかという判断である。長期に雇用する覚悟があるのであれば、無期転換権が発生すること自体、使用者にとって問題ないはずである。一方で、長期雇用を想定していないのであれば無期転換権が発生することは避けたいはずであり、通算契約期間が5年を超える前に雇用関係を終了させる必要がある。
雇入れの段階でこの点をはっきりさせず「上手く使おう」という考えは後々トラブルの原因となるため、まずこの点を雇入れの段階ではっきりさせることが重要である。
契約期間に上限を設けることができるのか?
仮に、長期雇用を想定せず、臨時の(短期の)雇用としたいという考えであれば、雇用契約の期間にあらかじめ上限を設けることを考える必要がある。有期雇用契約に上限を設けること自体は違法ではない。
例えば、「有期雇用契約は5年(4年でもよいが)を超えて締結しない」ことを明確にすればよい。これは就業規則や雇入れ時の労働条件明示のときにはっきりさせれば問題は生じない。ただし、「人や状況によって5年を超えることがある」「その時になってみないとわからない」という曖昧な状況は問題になる場合が多い。さらに、事前にこの点をしっかりと通知しておらず、4年経過した段階で突然「あと1年ですよ」というのも問題である。そうした問題がある場合には雇い止めが認められないリスクが生じる。
ただ、運用上のルールを明確に示し、そのルールを順守すれば契約期間に上限を設けることは可能で、当初の予定通りの期間で雇用契約を終了しても雇い止めが無効となるリスクは小さいといえる。
逆にそうした最初のルールを遵守できないのであれば、契約期間に上限を設けていたとしても雇い止めが無効とされるリスクがあり、契約期間の上限を定めた意味がなくなる。つまり、使用者にとってその時その時の『都合の良いやり方』は通じないのである。
有能な有期雇用社員はどうすればよいか
ここまで説明すると、「当初は短期雇用の予定だったが、途中で長期に働いてもらいたいと考えが変わった場合はどうする?」という疑問が出るかも知れない。その時は当該労働者と話し合い、無期雇用契約に切り替えてもらえばよいのである。
理想的には社内に『職種転換制度』などを整備し、雇用管理区分を転換させることが望ましい。つまり、『契約社員』としては契約期間には上限を設けた上で、必要な社員には本人と合意の上で異なる雇用管理区分で雇用を継続させることができる。雇用管理区分の整備が難しい場合は長期雇用を前提とした新たな雇用契約を締結すればよいのである。
なお、異なる雇用管理区分に転換する場合、必ずしも「正社員」という立場とする必要はなく、使用者の戦略で決めることができる。
結論
使用者側の戦略として有期雇用労働者をどのような役割と位置付けるかしっかり整理したうえで、契約期間に上限を設けることとするのであれば、そのことをあらかじめ労働者に対して明確にすることで、想定外の無期転換リスクは回避できる。
その上で、契約期間の上限を超えて雇用関係を継続したい労働者が現れたケースでは職種転換させた上で無期労働契約として雇用を継続することが最もリスクが小さい形といえる。
管理上の注意点
最後に、管理面で注意しなければならないのが期日管理である。いくら雇用期間に上限を設けても、実際に通算契約期間が5年を超えてしまえば無期転換権は発生する。この無期転換権は通算契約期間が5年を1日でも超えれば生じるため、既に勤続期間が4年を1日でも超えている有期雇用労働者と1年の雇用契約を新たに締結するとその時点で無期転換権が発生する。この点にはぜひ注意いただきたい。
特に注意が必要なのが、一番初めの契約期間である。月の途中に雇入れた場合などで管理上契約満了日を区切りの良い日にしようとした結果、少しだけ契約期間が長くなってしまう場合に思わぬところで通算契約期間が5年を超えてしまう場合がある。
今回紹介した事案では最初に短い訓練期間があったため通算契約期間が5年を超える結果となったともいえる。3月に雇入れていた場合、毎年の雇用契約が2月に満了するようにしていれば結果は違っていた可能性もある。
宍倉社会保険労務士事務所
電話 03-6427-1120
携帯電話 090-8595-5373
メール shishikura@ks-advisory.co.jp