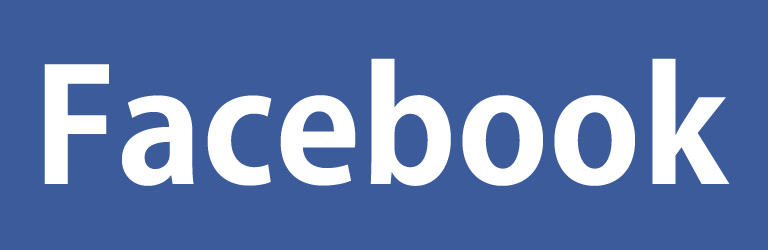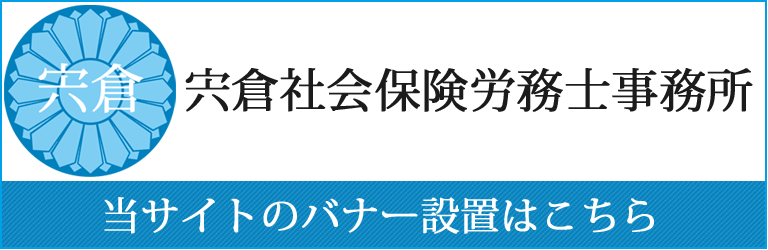労働問題を考える 『労働時間』ー④ 変形労働時間制度
平成28年9月
労働時間について解説をしてまいりましたが、今回はその4回目です。
前回の第3回から間隔があいてしまい、申し訳ありません。第2回と3回では36協定と特別条項について解説してまいりました。今回は第一回にご案内した、「(2)日によって業務の繁閑の差があり、法定労働時間を超える仕事をする必要のある日があることが分かっている場合」に法定労働時間を越えて労働できる方法として、『変形労働時間制度』について解説します。
第四回 変形労働時間制度
1.変形労働時間制度とは
日々の業務に繁閑の差がある場合に、法定労働時間である1日8時間1週40時間以内の労働とすることが困難であることがあらかじめ想定される場合に、一定期間の労働が「平均して」法定労働時間となるように日々の労働時間を定める(所定労働時間)ことができる制度です。(フレックス時間制度の場合は労働時間を労働者にゆだねることになります)。定められた制度・手続きに沿ってこの変形労働時間制度を正しく導入すると、法定労働時間である1日8時間の週に40時間を超えた労働をした場合でも、あらかじめ定めた所定労働時間以内であれば法定労働時間を超えて時間外労働したことになりませんし、割増賃金支払いの必要もありません。一方で、所定労働時間を超えて労働した場合には、仮に実際に労働した時間が1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えていない場合でも、時間外労働を行ったということになる場合もありますので注意が必要になります。時間外労働を行う場合には、前回までにご説明した36協定の届け出を行っていない限り、違法な時間外労働となりますので注意が必要です。
2.変形労働時間制度の種類
変形労働時間の制度に関しては、具体的に以下の4つの制度があり、法律上の定めは労働基準法32条の2項~5項にそれぞれ定めがあります。④の「1週単位の非定型的変形労働時間制」に関しては、事業の種類や従業員の人数等の制限があり、制度を採用できる事業場は限られておりますが、これ以外の制度に関しては制限がありませんので、どの事業場でも採用することが可能です。
①1ヶ月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
③1年単位の変形労働時間制
④1週単位の非定型的変形労働時間制
それぞれの制度に関する詳細の説明は第7回以降、個別に解説致する予定としています。今回はそれぞれの制度の簡単な特徴や留意点について説明いたします。
<1ヶ月単位の変形労働時間制>
定めるべき事項 以下の(イ)~(ハ)を就業規則、若しくは、労使協定で定め労働者に周知する
(イ)変形期間(1ヶ月以内の期間)とそれぞれの期間の起算日。
(ロ)期間中の各日・各週における具体的な所定労働時間をあらかじめ特定する。その特定した労働時間は各期間の起算日までには周知させること。
(ハ)各変形期間中の所定労働時間は1週間を平均して40時間以内となるようにすること。(特例事業は44時間)
制度がもたらす効果
各日、各週の労働時間(所定労働時間)を適正に定めた場合、特定の日や週の労働時間が法定労働時間を越えていたとしても、原則として、所定労働時間を越えない限り、時間外労働とはならず、割増賃金の支払も発生しない。
制度の運用上注意すべき点
一度定めた各日・各週の所定労働時間は、期間の途中で変更することはできません。実際の運用上、一旦定めた労働時間でも使用者側が任意に変更していると見られると、「1ヶ月単位の変形労働時間制度を『適切』に運用していない」として、通常の法定労働時間通りでの賃金再計算等を求められる可能性が高くなるので注意が必要です。
また、所定労働時間を越えて労働させた場合の労働時間は法定時間外労働となる可能性が高い。(所定労働時間がその変形期間の法定労働時間の総枠に満たないときは法定時間外労働とならない場合もある)。このため、割増賃金の支払は無論、36協定の締結・届出が必要となる。これを行っていない場合は違法になる。
<フレックスタイム制>
定めるべき事項
下記(イ)~(二)のうち(イ)は就業規則に明記し、(ロ)~(二)に関しては労使協定を締結して届け出なければならない。
(イ)始業・終業の時間は労働者の決定にゆだねていること。
(ロ)対象労働者
(ハ)「清算期間」(1ヶ月以内)を定めて、「清算期間」の総労働時間を定める。尚、清算期間の総労働時間は、期間を平均して1週40時間を超えない範囲(特例事業は週44時間)で定めなければならない。
(二)標準となる1日の労働時間
上記、(イ)~(ニ)のほか、コアタイムやフレキシブルタイムを定めることはできるが、その場合はそれぞれの開始・終了時間を労使協定で定めなければならない。
運用上注意すべき点
清算期間で、実際に労働した総労働時間が法定労働時間の総枠を越えていたら、越えている時間は法定時間外労働となり、割増賃金の支払や36協定の締結等の必要もある。また、実際の総労働時間が定めている総労働時間を下回った場合の調整に関しては手続上の注意を要する。詳細は別途案内する予定。
<1年単位の変形労働時間制>
定めるべき事項
以下の事項を労使協定で締結し、届出なければならない。
(イ)対象労働者の範囲、対象期間(1ヶ月を超え1年以内)と対象期間の起算日
(ロ)労働日と労働日ごとの労働時間。原則として対象期間の全期間にわたって予め定めることが求められる。ただし、例外的に1ヶ月以上の期間を区分している場合、最初の期間の労働日と労働時間だけ決め、以降は各期間についての労働日数と総労働時間を定めればよいとしています。この場合、各期間の具体的な労働日と各日の労働時間については期間開始の30日前までに労働者の過半数代表の同意を得て書面により定める必要がある。
(ハ)特定期間
対象期間中の特に業務が繁忙な期間について設定することができる。特定期間は『必ず定めなければならない』ということではないが、必須協定事項であるため、定めない場合でも『特定期間は定めない』とする必要がある。また、一度定めた特定期間は対象期間中に変更することはできないので注意が必要。
(二)協定の有効期間
制度がもたらす効果
各日・各週で定める労働時間は対象期間を通した平均で週40時間以内(特例事業も同じ)としなければならないが、40時間以内であれば、1日10時間・1週間52時間を上限として所定労働時間を定めることができる。ただし、一定の時間以上にできる回数等に関して細かなルールがあるので、ご確認ください。
注意すべき事項
この、1年単位の変形労働時間制度は最長1年に及ぶ長期間の制度であるため、運用上のルール等も細かく定められている。詳細は『労働時間』の第8回で解説する予定ですが、重要な注意点をここで3点説明します。
(1)途中入社と途中退職
対象労働者は対象期間を通じて勤務を継続することを前提に、その対象期間を平均して週40時間を達成すればよいとされています。従って、期間の途中で入社した社員や退職する社員等、対象期間の全期間勤務しない場合、「あらかじめ定められた所定労働時間」をそのまま適用することはできず、当該社員が対象となっていた期間における労働時間が週平均40時間を超えているかどうかを確認し、別途清算する必要がある。清算に関する具体的な定めは労働基準法32条4項の2に定められている。
(2)対象期間中の途中変更
期間の途中で変更できない点については、1ヶ月単位の変形労働時間制度と同様だが、1ヶ月単位の変形は途中変更してしまった場合に、その変更した当該対象期間のみが無効になる。これに対し、1年単位の変形労働時間制は全期間を通しての途中変更がでず、一部でも変更した場合は、その全期間が無効になってしまう恐れがある。このため、制度の採用にあたっては充分な検討が必要といえる。やむを得ず変更の必要が発生した場合は、制度を一度廃止し、対象者全員を変形期間中の退職者と同様の手続きで賃金の清算をしなければならない。
(3)労働日数・時間の限度
一か月単位の変形労働時間と異なり、労働時間が平均して週40時間以内となっていればどのように定めてもよいということはなく、労働できる日数、労働時間には限度が定められているので注意が必要です。
<1週単位の非定型的変形労働時間制>
必要な手続き
当該制度を導入すること、及び、40時間以内となる週の所定労働時間を定めた労使協定を締結し届け出る。 実際の運用では、各日の労働時間をは、その前週末までに定め、労働者に書面で通知する必要がある。
制度がもたらす効果
1週間の法定労働時間は40時間と通常の法定労働時間と変わらないが、1日10時間までであれば労働させても法定労働時間外労働とはならない。最大のメリットは、1週間前までに翌週各日の労働時間を労働者に通知すれば良いため、需要の変動を直前まで予測しにくい場合でもより柔軟に対応できる。さらに、緊急でやむをえない事由がある場合には、ぞの前日までに労働者に書面により通知すれば変更することも出来るとされている点にある。
適用できる事業所について
この制度を採用できるのは小売・旅館・料理・飲食の事業で30人未満のものに限られている。全ての事業所で適用できるということではないので注意が必要。
3.変形労働時間制度に共通する特徴
導入するメリット
全ての制度に共通して言えるのは、変形労働制は、一定の期間に対する所定労働時間を定めて、その定めた所定労働時間が『平均』して週の法定労働時間以内になっていれば、特定の日や週の労働時間が法定労働時間より長くなることが許され、法定時間外労働とはならず、原則として割増賃金の支払いも不要となるということです。使用者にとっては、繁忙期の割増賃金が抑えられるメリットがある一方、労働者にとっても、閑散期の労働時間を短くすることができるというメリットがある。
導入するにあたっての注意点
最大の注意点は、各制度でも説明していますが、制度を適切に運用しなければ制度自体が認められない可能性があるということです。そうなった場合には通常の法定労働時間の適用となり、1日8時間・週40時間を超える労働時間に対しては割増賃金の支払い義務が発生し、最悪の場合、2年間過去に遡って給与の再計算を求められる恐れがあります。
また、その「運用上の注意点」として最重要なのは、1ヶ月単位の変形労働と1年単位の変形労働はいずれも、あらかじめ定めた所定労働時間を変更できないということです。この点は極めて重要なので繰り返しご案内しております。
4.特例事業が導入する変形労働時間制度について
最後に特例事業に関して、制度によって取扱いが異なるので、確認の意味で整理します
1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制を採用する場合には、週の平均労働時間が『44時間』となる特例が適用され、一般の事業より長い時間が認められている。その一方で、1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制では『44時間』の特例は適用されず、平均して週40時間を上回ってはならない。このことにご注意ください。
特例事業とは(特例事業については第一回でも触れましたが、改めて確認します。)
労働基準法 施行規則25条2項で以下の定めがあります。
使用者は法別表第1 第8号、第10号(映画の製作の事業を除く)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定に関わらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。というものです。尚、第8号は商業、第10号は映画・演劇業、第13号は保健衛生業、第14号は接客娯楽業となっています。
変形労働時間制度は適切に制度を導入した場合には、使用者・労働者双方にとってメリットのある制度です。正しく導入するためのノウハウご相談についてはお気軽にお尋ねください。
宍倉社会保険労務士事務所
電話 03-6427-1120
携帯電話 090-8595-5373
メール shishikura@ks-advisory.co.jp
住所 東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第2ビル802